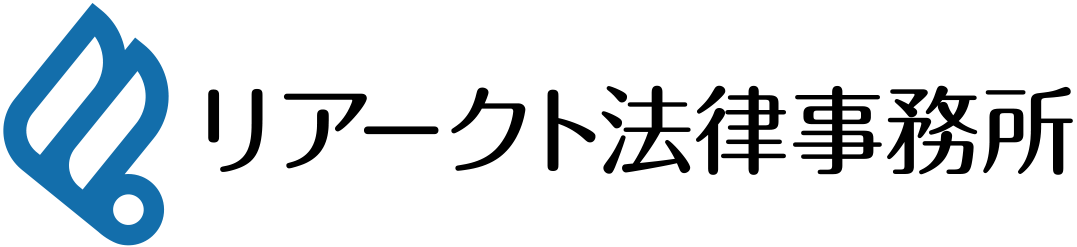契約実務のポイント(契約期間について)
ビジネス上で契約書を取り交わす際、意外と見落としがちな点が「契約期間」です。
多くの場合、取引内容については喧々諤々の議論をしていても、こと「契約期間」となると、「まぁ、将来のことは分かりませんし、とりあえず1年くらいで…。」としていることも多いのではないでしょうか。
しかし、契約書上の「契約期間」の条項は、「その契約が有効に存続するのは、いつからいつまでか?」を定めたものですから、実は、取引内容に負けず劣らずに重要なものです。
では、「契約期間」を考えるにあたっては、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
① 契約期間の定め
一番大切なことは、「契約期間が『いつからいつまで』なのか」です。
契約期間が長すぎれば、必要以上に契約上の拘束を受けることになりますし、契約期間が短すぎれば、必要となるときには期限が切れていた、と言うことになりかねませんから、適切な範囲で定めるようにしましょう。
契約期間の定めは、
「本契約の有効期間は、令和4年4月1日から、令和5年3月31日までとする。」とか「本契約の有効期間は、令和4年4月1日から1年間とする」
などと規定されることが一般的です。
期間満了日が休日の時はどうするのか、契約日を含めるのかという点を注意しながら、明確に記載することが適切です。
1回きりの契約(例えば、骨董品の壺の売買など)の場合には、「期間」で契約を定める必要がありませんから、契約期間を定めるのではなく、売買を履行する「期限」を定めることになります。
契約期間の定め方は、和暦でも西暦でも、有効性に問題はありません。それぞれの業界で一般的な記載をするとよいと思います。
(ちなみに、弁護士業界では和暦が一般的ですが、最近は西暦派も結構見かけます。)
② 契約の更新に関する定め
次に大切なことが、「契約の更新に関する定め」です。
どのような場合に、契約期間終了後に契約が更新されるのかを定める条項です。
そもそも契約の更新は必要ないのか、更新通知を出すなど更新に一定の手続を必要とするのか、自動更新とするのかといった点を考える必要があります。
自動更新の場合、契約の更新に関する定めは、
「契約期間の満了日の1か月前までにいずれの当事者からの意思表示がない場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする」
などと規定されることが一般的です。
上記の例のように自動更新とされていることも多いと思いますが、当方が義務を負う場合などには、自動更新ではなく、期間経過ごとに更新契約を締結し直すということが必要かもしれません。
③ 中途解約に関する定め
最後に大切なことは、「どのような場合に中途解約をすることができることになっているか」です。
中途解約に関する定めは、
「甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して2か月前までに書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。」
等と規定されることが一般的で、このような定めがある場合には、たとえ、契約期間が「10年間」と規定されていても、2か月前に解約通知を送れば、中途解約することができることになってしまいます。
例えば、契約が10年間続くことを前提として、その履行のために高額な設備投資をしているような場合に、上記の例のように解約通知を送った2か月後に解約できるような規定となっていれば、とても困ることになりかねません。
そのようなことにならないためには、そもそも中途解約に関する定めを設けないとか、中途解約をするためには何らかの条件を設けるなどと言った工夫が必要となります。
一般的には、自社にとって契約が長期間存続していた方が良い場合には、
・契約期間を長くする
・契約更新の定めを、同一条件で無制限に自動更新するような条項にする
・中途解約に関する定めを定めない
とすることが自社に有利になります。
また、契約が長期間存続しない方が良い場合には、その逆を考えればよく、
・契約期間を短くする
・契約更新の定めを定めないか、双方の協議・合意により更新することにする
・中途解約に関する定めを、できる限り自由に中途解約できるように定める
ということになります。
同じ契約形態であっても、適切な「契約期間」の定め方は千差万別です。想定外の事態を発生させないためにも、契約内容や取引の相手方、契約の目的に応じて、適切な契約期間を定めることが大切です。
今後、契約書を作成する際には、「契約期間」にも注意を払ってみてはいかがでしょうか。
(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)
執筆日:令和4年5月17日