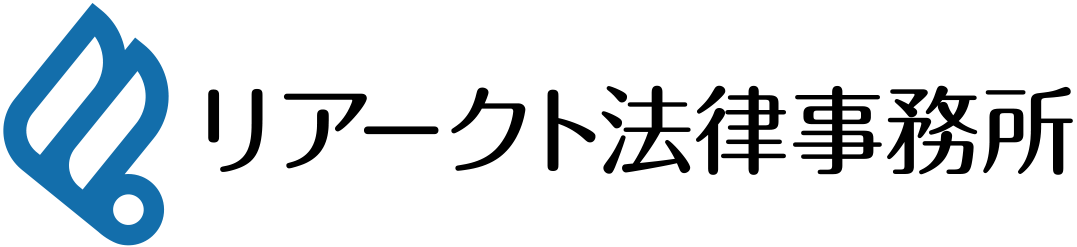パロディと著作権(YouTube動画)
1.動画の公開と著作権の侵害について
先日、人気Youtuberグループの「東海オンエア」さんが、Youtubeにアップロードしていた「【超約ぐりとぐら】『てつとゆめ』」が、福音館書店さんから著作権の申立てを受けて削除された、というニュースが、Yahooニュースに取り上げられていました。
日本では、漫画やアニメの登場人物、ストーリーを題材とした二次創作が多く行われており、また、楽曲についても「替え歌」といった形で楽しまれています。
これらは、いずれも「パロディ」として認知されていますが、法律上、「許されるパロディ」と「許されないパロディ」が明確に線引きされているわけではありません。
諸外国では、要件を満たした「パロディ」が保護されることが法律で定められていたり(フランス)、「許されるパロディ」の基準が判例上確立していたり(アメリカ)するようですし、日本でも、平成25年には、文化庁において「パロディワーキングチーム」が組織されて、「パロディ」の法制化について検討されていたようですが(※1)、法制化は見送られていますし、判例上、要件が確立しているとは言いにくいのが現状です。
パロディは、おおよそ、「既存の著作物を利用すること」に特徴がある表現です。
そのため、「パロディの法的問題」を簡単に説明するとすれば、そのような表現(パロディ)において、「既存の著作物を利用することが許されるかどうか」(許されるとすれば、どのようなパロディであれば許されるのか?)という問題であると言えます。
パロディの問題を整理してみたいと思います。
2.著作権とはどういう権利か?
まず、大前提として、著作権者は、著作権が侵害されている場合、その侵害の停止を請求することができます(著作権法112条1項)。
Youtubeなどで、投稿された動画に「著作権侵害」があるとして削除されるのは、この条文が理由です。
そのため、「動画X」が、「絵本Y」の著作権を侵害している場合には、その削除をしなければならない、ということになります。
では、「著作権を侵害している」とは、どういうことをいうのでしょうか?
世間一般では、「著作権」とまとめて呼ばれることが多いのですが、実は「著作権」とは、色々な権利の総称のことをいいます。
著作権の有する権利(広義の著作権)の中には、大きく分けて、「①財産的価値のあるもの((狭義の)著作権)」と「②人格的価値のあるもの(著作者人格権)」があり、また、①と②の中にも、それぞれ別々の権利がある、という構造になっています。
これを図にまとめると、次のとおりです。
いずれの権利も、著作権法で定められているものです。
逆から言えば、著作権法で定められていない権利は、(そもそも権利がないので)著作権者といえども行使できない、と言うことです。
そこで、「著作権を侵害している」というときには、「著作権」の中でも、何の権利を侵害しているのかを意識することが肝要です。
3.パロディには、どのような法的問題があるのか?
パロディの場合には、その性質上、元となる表現(絵本Yの表現)の改変を伴うことが一般的ですから、主に問題になるのは「翻案権」や「同一性保持権」であると言われています。
では、どのような場合に「翻案権」や「同一性保持権」の侵害になるかというと、「他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得」させるような場合には、侵害になると解されています(※2)
「本質的な特徴」や「直接感得」という難しい言葉を使っていますが、易しく言えば、動画Xを見て、直接、絵本Yの表現を感じられるようなものは侵害となる、ということです。
そのため、動画Xが絵本Yを前提としたパロディであったとしても、動画制作者によって「新たな創作」がなされていて、それが大部分を占めているなど、もはや、動画Xを視聴してもパロディされる側である「絵本Y」の表現が直接感じとれないものに昇華されていれば、動画Xは、「翻案権」や「同一性保持権」の侵害には当たらないことになる、と考えられます。
また、著作権法で保護されるのは、具体的な「表現」であり、「アイディア」は保護されません。
そのため、動画Xが、絵本Yのアイディア部分や創作性のない部分を利用しているに過ぎない場合には、そもそも「翻案」に当たらないと言えるでしょう。
これらのことからすれば、動画Xと絵本Yの「ストーリーの大筋」が似ている(踏襲している)としても、それだけをもって、絵本Yの著作権者が、翻案権や同一性保持権の侵害と主張することは難しいように思われます。
4.著作権が制限される場合
では、「翻案」にあたる場合には、他人の著作物を利用することは許されないのでしょうか?
著作権法30条から47条の7は、「著作権が制限される場合」について規定しています。
一番有名なものは、「私的使用のための複製」(30条)です。
例えば、著作物を複製する権利(複製権)は、本来、著作権者だけが有するものですが(21条)、個人的に使う場合(私的利用のため)には、著作物を複製してもよいよ(30条)、ということです。
そこで、パロディには、原著作物への批判、論評、風刺という側面があることから、パロディは、著作権法で著作物の利用が許されている「引用」(32条)にあたるとする見解があります。
著作権法32条1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この見解には、
① 目的上、代替不可能であること
② 必要最小限の引用であること
③ 現作品の著作権者の経済的不利益が僅少であること
を要件として「引用」を認めようとする見解や、
① パロディから「原作への風刺・批判の意図が、作品から客観的に認識できること」
② 「引用」以外の他の著作権法32条1項に係る要件を満たすこと
により、「引用」の類推適用を認めようとする見解があるようです。(※3)
私見ですが、パロディには、ユーモア、すなわち世の中に笑いを生む要素があることからすると、上記の要件は少し厳しすぎるのではないかと思っています。
関連する裁判例として、俳句について、「Aさんが作った俳句を、Bさんが添削して(修正して)雑誌に掲載したこと」が、著作者人格権を侵害しているかどうか、ということが争われた裁判例(※4)があります。
この裁判例では、「本件各俳句の投稿当時、新聞、雑誌の投句欄に投稿された俳句の選及びその掲載に当たり、選者が必要と判断したときは添削をした上掲載することができるとのいわゆる事実たる慣習があった」と認定し、「事実たる慣習が認められる場合には、当事者間において特にこれを排斥しあるいはこれに従わない旨の意思が表明されていない限り、慣習によるとの意思があったものとして法的に取り扱われることがあり得るのである(民法92条)」と述べられています。
パロディ自体、世間にありふれて楽しまれており、多くの人に受け入れられているものですし、表現の自由の観点から、「許容すべきパロディ」が存在すること自体は、概ね異論がないものと思われます。
そこで、アメリカにおける「フェアユース」のように、原著作物を変容させるものであって、新しい文化等の創作に寄与し、著作権者の原作品・派生的作品の市場に実質的なく影響を与えないようなパロディであれば、既に、日本国内において広く認める下地が備わっており、裁判上もそのことを認めていくことが良いのではないかと考えています。
5.著作権法違反には、刑事罰が定められていること
さて、著作権侵害の話に戻ります。
上述のとおり、「パロディ」が許されるかどうか、許されるパロディと許されないパロディの境目はどこなのか、ということについて、まだまだ結論が出ているとは言えません。
そこで問題となるのが、「著作権法違反には、刑事罰が科せられている」ということです。
著作権法119条1項
著作権…を侵害した者…は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ただし、これは「親告罪」といって、被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない(つまり、罪に問えない)こととされています。
そのため、「パロディ動画X」の制作者としては、仮に、「絵本Y」の著作権者から、著作権を侵害するとして動画Xの削除を求められた場合、
動画Xは、法律上も許されるパロディであると思うけど、もしかしたら許されないかもしれないし、著作権法違反となってしまえば、お金の問題はともかく、刑事罰が科せられることになりかねないから、削除しておこう。
削除すれば、「絵本Y」の著作権者も、告訴することまではしないだろう。
と考えるのではないかと思います。
ただ、これでは、表現行為への萎縮効果が極めて大きく、1つ1つは小さくとも、日本のパロディ文化が衰退する一歩となりかねません。
これらのことからすればそこで、パロディをする側として、前述の「引用」や「フェアユース」といった視点を持ちつつ、節度をもってパロディをすることが大切なことは言うまでもありませんが、権利者側としても、パロディ文化に配慮しつつ、相当な範囲で権利行使をするように努めることが必要であると思います。
※1 文化庁 パロディワーキングチーム(議事要旨)
※2 モンタージュ写真事件(最判S55.3.28)参照
※3 青木大也「著作権法におけるパロディの取扱い」ジュリスト1449号55頁(2013)
なお、見解について「田村善之『著作権法概説(第2版)』243頁」「横山久芳『法学へのアプローチ(Ⅱ)著作権法-「パロディから考える著作権法入門」』法学教室380号33頁」
※4 東京高判H10.8.4 判時1667号131頁
(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)