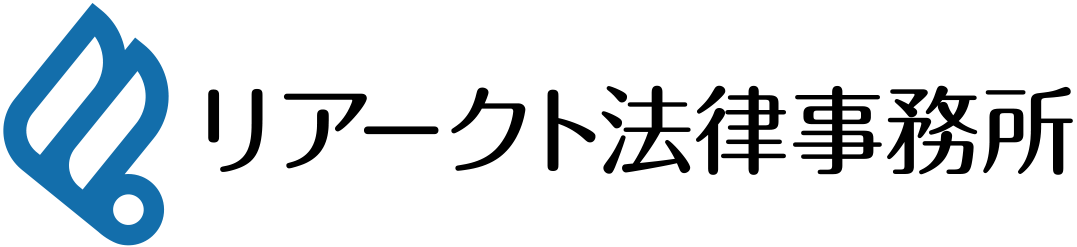弁護士費用を裁判の相手方に請求できるのか?
1.弁護士費用は誰が払うの?
訴訟事件のご相談をいただく際、
「勝訴したら、先生にお支払いする弁護士費用は、相手方に請求できるのですか?」
と聞かれることがあります。
原告側であっても、被告側であっても、
「当方の言い分が正しく、相手方が間違っている。そのことを、相手方が訴訟前に認めてくれれば、裁判にもならず、弁護士費用がかかることもなかったのだから、余計にかかることになった弁護士費用は相手方に払ってほしい。」
というお気持ちはよく分かります。
ただ、残念ながら、このご質問に対する回答は、
「弁護士費用は、基本的に、依頼者ご本人の負担になります。」
というものになります。
そこで、本コラムでは、「弁護士費用の負担者」についてまとめていきます。
2.原則と例外
上記の回答の意味を、もう少し詳細に説明すると、
- 原則として、裁判に勝ったとしても、弁護士費用を請求することはできない
- 例外として、一部の事案においては、弁護士費用を相手方に請求することができる
- しかし、例外として弁護士費用請求できるとしても、実際に支払った弁護士費用全額を請求することはできない
という意味です。
裁判では、多くの場合に「法律上の請求権」の存否を争うことになりますが、「法律上の請求権」の種類を大きく分けると、次の2つに分けることができます。
① 契約上の権利を実現するもの
② 不法行為により被った損害の賠償を求めるもの
①の類型では、基本的に、弁護士費用の請求をすることはできません。
一方、②の類型では、弁護士費用の請求をすることができます。
但し、②の類型で、弁護士費用の請求をすることができる場合でも、その額は、実際に支払った弁護士費用ではなく、「被った損害額の10%を目安に、裁判所が決める額」とされます。
この違いがどのような理由で生じているかについて、裁判例を分析してみると、
- 法律上は、弁護士に頼まなくても訴訟追行を行うことができる(※ 1)。
(弁護士を委任するか、自分自身で対応するかは、自由に選ぶことができる。)
- 契約締結時に、任意の履行がされない場合を考慮して、契約の内容を検討したり、契約を締結するかどうかを決定することができる(※ 2)。
- ①は、契約の目的を実現して履行による利益を得ようとするものであるが(※ 2)、②は、侵害された権利利益の回復を求めるものであって(※ 3)、性質が異なる。
- 現在の訴訟は専門化されており、技術化された訴訟追行を当事者に要求するので、一般人が単独で十分な訴訟活動をすることは不可能に近い(※ 1)。
- 不法行為による損害を被った者は、相手方から容易にその履行を受けられない場合、訴訟を提起しないと権利を実現できない(※ 1)
というようなことが考慮されているようです。
このように分析してみると、裁判所は、「法律上、裁判をするためには弁護士を頼まなくてもよい」が、「弁護士に頼まないと、適切に訴訟追行をすることは事実上難しい」と言っているように見え、この両者は矛盾しているようにも感じます。
しかし、裁判所は、交通事故のように「見知らぬ第三者から、突然に損害を被った場合」(②)と、「契約を締結した相手方との間で、契約の不履行があった場合」(①)には、質的な差があるということを重視しているのだろうな、と思います。
3.その他、弁護士費用が認められる類型
上記①の「契約上の権利を実現するもの」でも、以下のような事件類型では、弁護士費用が認められています。
- 勤務中に事故にあった従業員が、会社に対し、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求する場合(※ 4)
- 病院を受診した患者が医療過誤を受け、診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合(※ 5)
- 建築工事にかかる請負契約を締結したが、建築物に瑕疵があり、その損害賠償を請求する場合(※ 6)
これらの事件類型は、
- 訴訟上、主張・立証する要素が、不法行為にも基づく損害賠償と変わらない
(債務不履行構成と不法行為構成の、どちらの請求をすることもできる)
という要素があることから、例外的に、弁護士費用を請求することができるとされています。
抽象的には、不法行為による損害賠償(②)の場合と、同じロジックが用いられており、「ある権利を訴訟上行使するためには、弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権である」場合には、弁護士費用が認められています。
そのため、弁護士費用を請求できる類型を整理すると、以下のようになります。
① 契約上の権利を実現するもの
→原則として、弁護士費用は請求できない
→例外として、一部の事件類型では、弁護士費用を請求することができる
② 不法行為により被った損害の賠償を求めるもの
→弁護士費用を請求することができる
4.契約上の根拠がある場合はどうか?
では、弁護士費用を請求することについて、例えば、以下のような契約上の根拠がある場合はどうでしょうか。
(このような条項を、「弁護士費用加算条項」といいます。)
第X条(損害賠償)
本契約に定める他、甲及び乙は、故意若しくは過失により、又は、本契約若しくは個別契約に違反したことにより、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。)を直ちに賠償する責任を負う。
民法521条2項は、
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
と規定しています。
上記のような契約も、直ちに法令違反とは言えないと考えられますから、有効と考えられます。
なお、事業者対消費者の契約(いわゆる消費者契約)の場合には、消費者契約法が適用されます。
そして、消費者契約法には、「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」(9条)という条項があることから、契約上、弁護士費用加算条項があったとしても、その全部が有効になることはないと思われます。
さて、契約上、上述のような弁護士費用加算条項があり、そのことを理由として「総損害額の1割を弁護士費用」として請求した裁判例があります(※ 7)。
この裁判例では、「実際にかかった弁護士費用」を請求した事案ではなく、「合理的な弁護士費用」として「総損害額の1割」を請求した事案ですが、「契約上の権利を実現するもの」(①)について、「総損害額の1割」の弁護士費用を裁判所が認容しています。
また、平成24年最判(※ 4)は、損害の範囲について、
弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
と述べて、総損害額の約1割の弁護士費用を認めています。
そのため、弁護士費用加算条項によって、弁護士費用が「損害」に含まれるとしても、そもそも「相当因果関係が認められない範囲」については「損害」として認められないと考える余地があります。
これらのことからすれば、契約書上、弁護士費用加算条項が規定されていれば、少なくとも「総損害額の1割」は合理的な弁護士費用として請求することができる、と言えそうです。
5.弁護士費用加算条項があれば、実額を請求できるのか?
では、弁護士費用加算条項を基に、支出した弁護士費用の全額(実額)を請求することはできるでしょうか?
この点について参考になる裁判例が、東京高裁平成26年4月16日判決(※ 8)です。
本判決は、マンション管理組合が住民に対し、滞納した管理費や弁護士費用等を請求した事案で、当該マンションの管理規約に、「違約金として弁護士費用を請求することができる」との規定があった事案です。
国土交通省が公開している「マンション標準管理規約(単棟型)」には、以下のような規定があり、本事案でも、同様の定めがあったようです。
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
上記4で言及した「弁護士費用加算条項」は、弁護士費用を「損害」の一部としていますが、マンション標準管理規約では、弁護士費用を「違約金」としていることに違いがあります。
少し長くなりますが、本判決(※ 8)では、
違約金とは、一般に契約を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとって、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。しかし、それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。そこで、本件管理規約36条3項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請求することができるように定めているのである。このような定めは合理的なものであり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される(その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。)。
と述べて、弁護士費用の実額が違約金として認められています。
この裁判例は、住民が滞納した「マンションの管理費」を請求するものであって、マンション管理組合は営利目的の団体ではなく、弁護士費用が管理組合の持ち出しになってしまえば、実際には、他のマンション住民が負担することとなって衡平を失する、という特殊性があります。
そのため、
・「損害」として請求する場合には、弁護士費用の全額は請求できない
・「違約金」として請求する場合には、弁護士費用の全額を請求できる
として、単純に整理することはできないと思います。
しかし、契約書の文言や弁護士費用を請求する際の法的な位置付けを検討することによって、相手方に対し「弁護士費用の全額を請求する余地がある」ように思われます。
そのため、弁護士費用加算条項を設ける場合には、具体的な算定方法や上限金額などを定めることとして、契約上、「合理的な弁護士費用」がいくらであるのかを明示することがよいのではないでしょうか。
6.まとめ
今回は、弁護士費用について解説してきました。
一部、弁護士費用を相手方に請求できる場合もありますが、その場合でも、認められる金額は損害額の1割となることが多いことがご理解いただけたと思います。
また、お互いの言い分が食い違って訴訟となった場合でも、実務上、「和解的解決」をすることも多く、和解により解決する場合には、「お互いに弁護士費用を請求しない」とすることが一般的です。
そのため、ご依頼いただく際には、冒頭に記載したとおり、
「弁護士費用は、基本的に、依頼者ご本人の負担になります。」
とご説明し、費用についてご納得いただいた上で、ご依頼をいただくようにしています。
※ 1 最高一小判昭和44年2月27日最高裁判所民事判例集23巻2号441頁
※ 2 最高三小判令和3年1月22日最高裁判所裁判集民事265号95頁
※ 3 最高一小判昭和48年10月11日最高裁判所裁判集民事110号231頁
※ 4 最高二小判平成24年2月24日最高裁判所裁判集民事240号111頁
※ 5 大阪高判平成31年4月12日判例時報2443号27頁
※ 6 東京地判平成29年3月23日D1-Law.com判例体系〔28253226〕
※ 7 東京地判平成27年10月27日D1-Law.com判例体系〔29014330〕
※ 8 東京高判平成26年4月16日判例時報2226号26頁〔28223023〕
(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)
以上